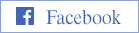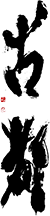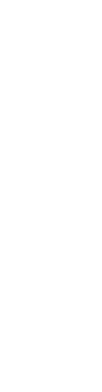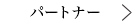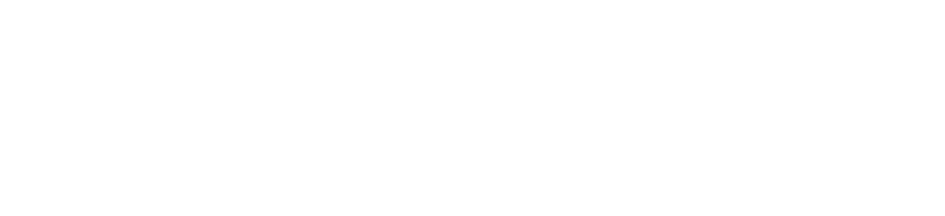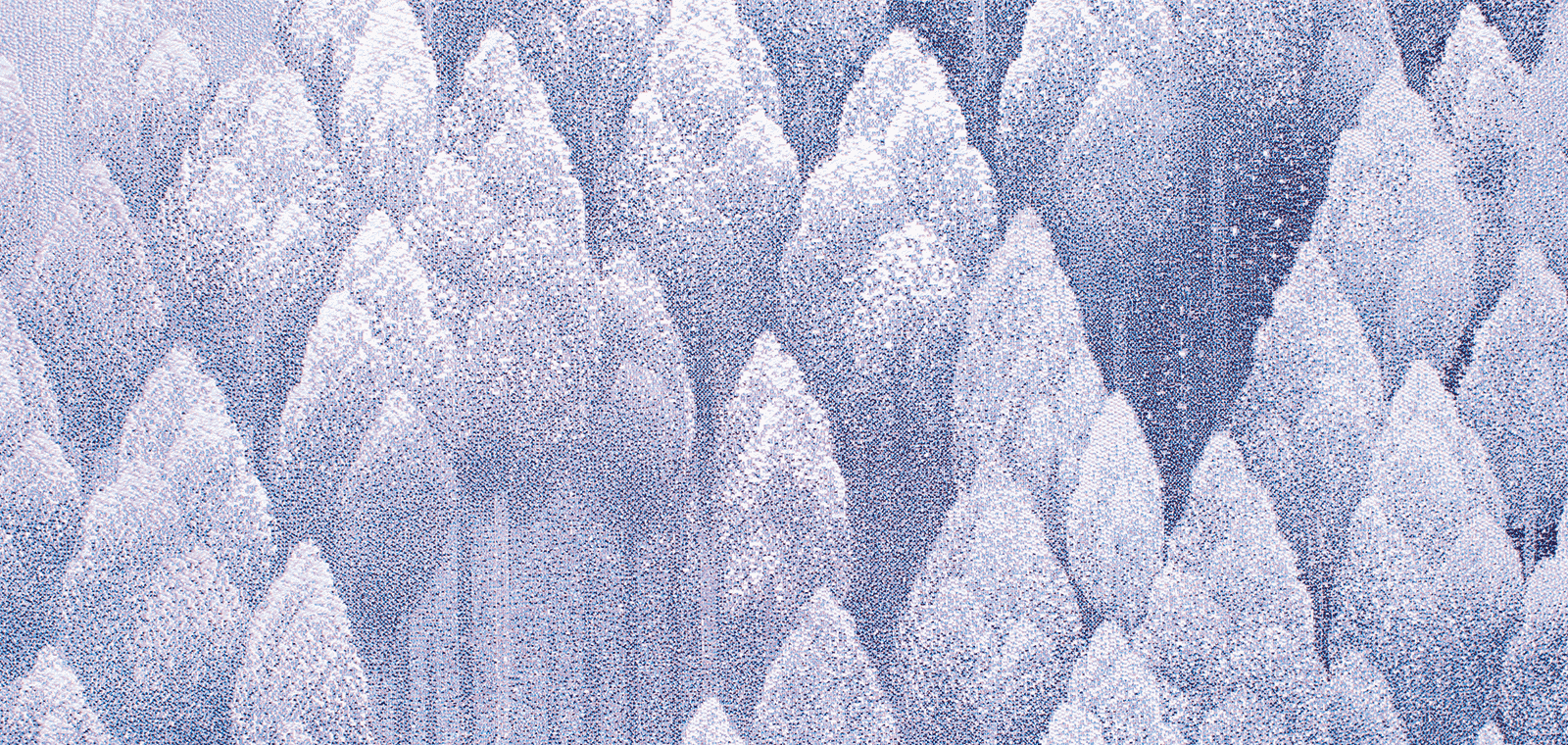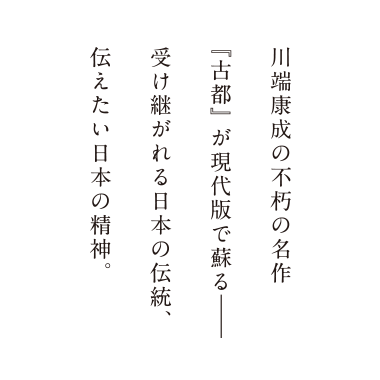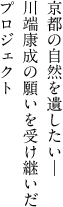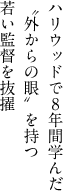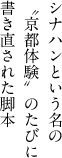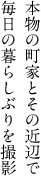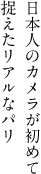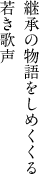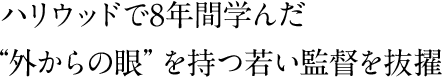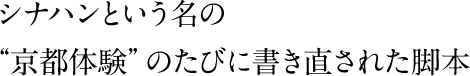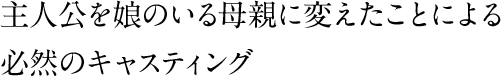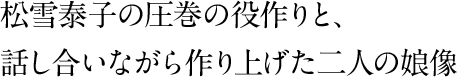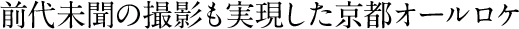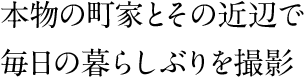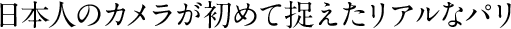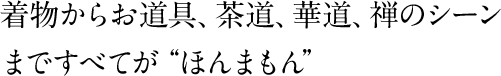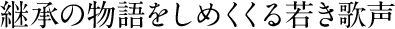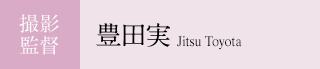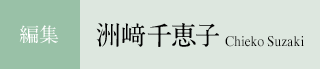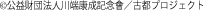数々の地域開発映画を手掛けてきたプロデューサーの伊藤主悦は、映画製作を通して日本各地の町興しをすることで、“人を興したい”と考えていた。これまでは、地方の町を日本全国に発信してきたが、折しも2020年にオリンピックを控える今、今度は世界へと発進したいと企画を練っていた。海外へ向けるならやはり京都だろうと思っていたところに、NPO法人「遊悠舎京すずめ」の土居好江理事長から川端康成の『古都』を映画化したいがどうすればいいかという相談を持ちかけられる。
京都の魅力を発掘・発信するために京すずめを設立した土居理事長は、かねてより親交のある川端康成記念會理事長の川端香男里氏から、「美しい京都の自然を遺し守り、後世にいかに引き継ぐのか」が、川端康成が生涯かけて抱いていた想いだと聞いていた。さらに、川端氏の「京すずめの京都が京都らしくあり続ける運動は、日本の開発の危機に対する極めて敏感な反応だと思います」との言葉を深く受け止め、京都の文化発信について書道家の小林芙蓉と意見交換を続けてきた。
こうして2013年9月26日、意思を同じくする者たちが出会い、プロジェクトが始動した。
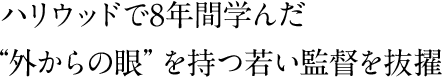
もっと深く京都を知るために、2014年11月からほぼ半年間、京都に暮らした伊藤プロデューサーは、街ですれ違った人や入った店の人などに積極的に話しかけて、数多くの“生の声”を集めた。それは、“家業を継がない”“町家を売った”など、伝統が壊れ始めている現状を伝えていた。危機感を覚えた伊藤プロデューサーは、京都の今を描く必要性を痛感し、過去に映画化された2作品とは異なる“現代版”を企画する。監督は若い世代に託すことになり、伊藤プロデューサーの提案で、ハリウッドで映画作りを8年間学んだYuki Saitoにオファーする。
ハリウッド映画に憧れて高校卒業後に渡米したSaito監督は、「24」のプロデューサー、ノーマン・パウエルに師事するが、ある時日本の名作をほとんど見ていないことを叱責される。日本の文化を表現するために今すぐ帰国しろと諭され、師の教えに従って10年、様々な作品に携わってきた。そして伊藤から『古都』の監督に抜擢され、日本文化に真正面から向き合えるチャンスが遂に来たと興奮したという。
伊藤プロデューサーと共に川端香男里氏を訪ねたSaito監督が、氏に「小説の精神を大切にしつつ、海外経験のある自分の感性で今の京都を描きたい」と語ったところ、「想いを継承するような作品にしてください」というのが氏からの唯一の要望だった。「あとは自由に感じたままにやってください」と言われて、身が引き締まったと監督は語る。
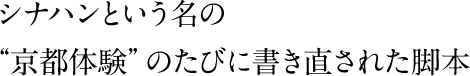
共同プロデューサーの岡本丈嗣から、主人公の千重子と同じ京都の室町の呉服問屋を経営していた親戚がいると聞いた伊藤プロデューサーは、彼の紹介で話を聞きに行く。それが、本作の京都プロデューサーを務める熊谷昌美、優希親子だ。熊谷家の町家を訪れた伊藤は「千重子さんと舞ちゃんがいた」と、企画書を読んだ熊谷は「まるで、うちのことが書いてあるみたい」と双方で驚き、その場で協力が決定する。
まもなくSaito監督も熊谷親子と対面し、それから約2年の間、町家での暮らしを“実体験”するために、伊藤プロデューサーと共に幾度となく訪れる。たとえば、熊谷は毎日お墓参りに行くのだが、ある時監督が同行し、つぶさに見聞きした様をその日のうちに脚本に落とし込み、千重子と舞の墓参りのシーンが生まれた。
さらに伊藤と監督は、川端康成の京都での足跡を追いかけた。資料で川端が好んだ宿や飲食店、頻繁に訪れた寺などを調べ、季節ごとに足を運んだ。京都へ行くたびに、共同脚本の眞武泰徳、梶本恵美と共に、脚本を大幅に変えるという作業が続き、脚本は50稿以上に及ぶ。ようやく完成した脚本を川端香男里氏に送ると、氏からは「ここには生きる希望がある」という言葉が届く。
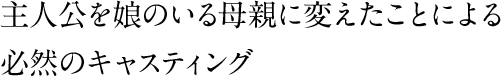
舞台は現代だが、最初の20稿目ぐらいまでは、原作と同じく千重子と苗子は20歳という設定だった。書き進めていくうちに、Saito監督は彼女たちを主軸にすると、伝統の継承が描けないことに気付く。しかし、主人公を母にすれば、彼女が20歳だった頃の昔のことも、母親になった現在も、そして20歳になった娘にどう受け継いでいくかという、川端香男里氏との約束も全部描けると思いつく。
実は監督には、どうしても仕事をしたい女優がいた。アメリカから帰ってきて、逆カルチャーショックに打ちひしがれていた時に励まされた映画『フラガール』の主演、松雪泰子だ。千重子と苗子を母親として想定していくうちに、松雪の顔が浮かび、監督は松雪宛に、あなたと映画を撮ることが目標だと打ち明けた“ラブレター”を書く。手紙に心を動かされた松雪は主演を即決する。
千重子の娘の舞、苗子の娘の結衣役にも、監督のたっての願いが叶う。舞には和の美を象徴する佇まいで神秘性があり、町家で暮らす様がはまりそうな橋本愛。イマドキの女の子のような浮ついた感じは全くないが、現代の女の子特有の揺らぎはある。やりたいことがなくて途方に暮れているが、瞳の奥にはやがて目覚める意志が宿っている。そんな舞のイメージは、橋本愛そのものだ。
一方、結衣は意志をむき出しに、感覚と感性で生きている。同じ京都でも舞と違って、緑に360度囲まれた山ですくすくと育ち、絵を描きたいとパリへと飛ぶ行動力もある。ストレートな目力があって、もちろん演技派でと考えた時に、成海璃子しかいないと確信した。
「3人全員がイメージ通りで、こんな幸せなことってあるんだろうかという気持ちでした」とSaito監督は振り返る。
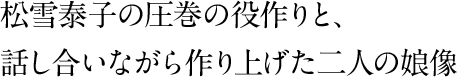
脚本作りから積極的に関わった松雪泰子は、役作りに関しても明確なヴィジョンを持っていた。幼い頃から日舞を習い、着物に対する造詣も深い。Saito監督は、母親の気持ちも含め教えられることばかりで、「千重子、苗子の本人と打ち合わせをしてるみたいでした」と笑う。さらに、二役に関しても、演じ分けは完璧だった。千重子から苗子に変わった時は、現場に入った瞬間から明らかに違っていたという。
監督から橋本愛には、千重子との距離感を大事にしてほしいと話した。心と心でつながってはいるが、千重子が纏っている宿命が母娘の壁になっているはずだと考えたのだ。今の20代から見て非常に感情移入しやすいキャラクターだということも留意してほしいと語った。
結衣のエピソードは、Saito監督のアメリカでの実体験をもとに描かれている。夢を抱いて海を渡ったけれど、現実は甘くなかったという過去を成海璃子に説明した。また、パリのシーンは『魔女の宅急便』をモチーフにしている。キキが自分を見失って飛べなくなるように、結衣は絵が描けなくなる。既に観ていた成海に、撮影前にもう一度観てもらった。
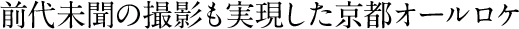
本作にとって、京都オールロケは必須だった。京都府、京都市のバックアップのもと、土居プロデューサー、熊谷プロデューサーを中心に、京都の様々な関係者の協力で実現した。その結果、妙心寺退蔵院、初めて映画カメラが入った鴨川の水源地である岩屋山志明院、北山杉の生産地域にある菩提の滝、皇室とつながりのある青連院門跡など、貴重な場所での撮影が実現した。
さらに、千利休時代から茶室に使用されていた、日本最古の人工林である北山杉は、中源株式會社が所有する林で撮影された。平安神宮を入れたのにも意味がある。明治時代にできた新しい神宮だが、町衆がお金を出して作った神社だ。京都は雅の街と言われるが、町衆や職人が最高の技術を磨いて天皇に献上することによって、栄えてきたが、雅の極みをつくりだした心意義を示す場所として紹介したかったのだ。また鴨川では、通常は難しいドローン撮影が敢行された。
Saito監督は、京都撮影時は「凛とした空気が現場中に漂っていて、氏神様に見守られているようでした。千年の文化を匂い立たせるようなロケ地が選べたと思います」と胸を張る。
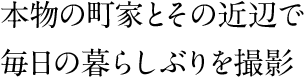
千重子の暮らす町家の、寝室、座敷、庭、舞の部屋、仏間、縁側などの生活部分は、すべて熊谷プロデューサーの大正末期に建てられた町家(国登録有形文化財)で撮影された。100年近く前、熊谷プロデューサーの祖父が建て、代々継承して住んできた家である。柱や床などあちこちに傷もあるが、Saito監督は「家にストーリーがある」からと、何も手を加えないで撮影した。熊谷家のリアルな暮らしぶりがいくつも反映されている。不動産会社が地上げに来たシーンは、監督が訪問中に本当にあった話。熊谷家の仏壇もそのまま使われ、母の遺影も写真だけ差し替えられた。
店部分と台所(おくどさん)、そして外観は、『古都』前2作のモデルとなった長江家住宅で撮影された。1822年から呉服商を営み、2005年に京都市指定有形文化財に認定された貴重な町家である。
熊谷プロデューサーの縁で、禅のシーンは妙心寺退蔵院で撮影、副住職松山大耕が自ら出演した。また、錦市場も組合の宇津理事長が知り合いのため、早朝の開店前に開けてもらった。店主たちも実際の人たちである。
舞の大学のシーンは、同志社大学で撮影された。エキストラもすべて同志社大学と同志社女子大学の学生たちで、村田晃嗣教授による授業シーンが収められた。書道教室の先生として、小林芙蓉も出演している。
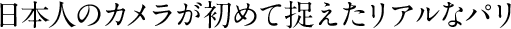
アートを駆使して北山杉を守ろうとしている結衣の留学先として、京都の姉妹都市であり、文化芸術の街という共通点もあるパリが選ばれた。
初めてパリにロケハンに行ったSaito監督は名所に惹かれたが、2回目に行った時に芸大生たちを取材した。彼らからこれからのカルチャーの中心は20区だと熱弁され、日本映画では撮影したことのない移民街を舞台に選ぶ。
パリでのロケ撮影は2015年12月にスタートする予定だったが、11月にテロが勃発する。撮影は中止となり、フィレンツェやプラハなど他の古都への変更も検討されるが、Saito監督はどうしてもパリで撮りたいと粘る。「人々のプライドが高く、セーヌ川と鴨川が流れ、伝統が息づいていて。パリと京都は双子だと僕の中で成立していたんです」。
3月には情勢も落ち着き、撮影は無事にスタートした。日本の撮影隊に驚いたフランスの国営テレビが、現場に取材に来たりもした。観光旅行ではまず見ることのできない、リアルなパリの一面がスクリーンに切り取られている。
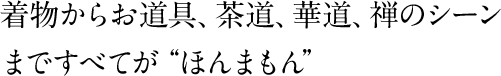
裏千家今日庵と池坊華道会支援は、熊谷プロデューサーとの縁で決まった。茶道のシーンでは茶道指導はもとより、お道具は裏千家のお家元から借りている。池坊専好次期家元は自ら出演、花を生けた。仏壇の横の小さな床の間の花など、お茶のシーン以外は、すべて池坊華道会のものである。
また、京都人にとって神社仏閣は心の寄りどころであり、自分に迷いが生じた時、退蔵院へ行き座禅を組むと迷いが吹っ切れるという熊谷プロデューサーの実体験をもとに、舞が退蔵院で座禅を組んだことで一歩を踏み出すきっかけとなる重要なシーンが作り上げられた。
衣装と美術は、京都の人々が昔から愛用している品々が集められた。なかでも着物は、京都織物卸商業組合、西陣織工業組合の全面協力を得て、熊谷プロデューサー、和文化プロデューサーの森荷葉、服部和子きもの学院の服部有樹子らの尽力で、最高の品々が揃えられた。
物語の重要なカギを握る、東山魁夷の画にインスパイアされた北山杉の帯は、熊谷プロデューサーと伊藤プロデューサーが帯問屋を6カ月かけて回って見つからなかったのが、京都の帯問屋・長谷川で偶然出会って感激した帯だ。
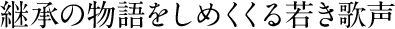
脚本の眞武からSaito監督に、中島みゆきの「糸」の歌詞が、本作の物語を表していて、川端康成の精神性ともつながっているから、是非主題歌として使用したいという提案があった。監督も改めて聞き直して驚いたという。
監督は継承の物語を表現するため、舞と結衣が歌っているイメージで、20歳くらいのシンガーに歌ってもらいたいと考えた。そうして探し当てたのが、監督が切ないけれど芯のある声に一目ぼれしたという新山詩織だ。アカペラでスタートしたのは、ラストシーンの教会につながる讃美歌をイメージしている。
締めくくりを「糸」にすると決めたことから、オープニングも帯を織る糸で始めた。続いて格子や瓦など京都のディテールを出しているのは、過去作へのオマージュだ。同じイメージから始めて、カメラが引いたところで、50年後の現代の京都が映る。
完成した映画を観た川端香男里氏からは、「ラストシーンは川端文学を象徴している」という、これ以上ない言葉が届いた。